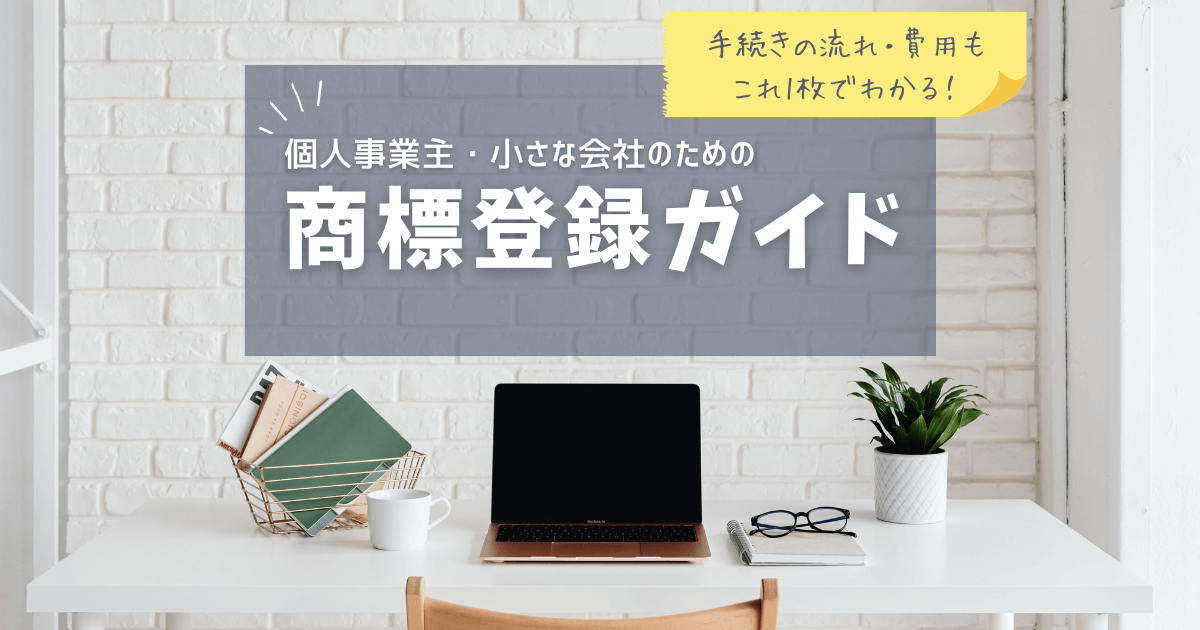商標登録の基本を押さえることで変わる3つの安心

商標とは?登録する意味や著作権との違いをわかりやすく解説
商標とは、商品やサービスの名前、ロゴ、マークなどを指します。お客さまに「これはあのブランドのものだ」とひと目で伝えるための、大切な目印です。
この商標をしっかり登録しておくことで、他の人が同じような名前やロゴを勝手に使うことができなくなります。
つまり、自分のブランドを守る「法的な力」を持つことになるのです。
よく混同されがちな著作権は、作品を作った時点で自動的に発生します。しかし、商標は登録の手続きをしない限り、法的には守られません。
たとえ長年使っていたとしても、第三者に先に登録されてしまうと、自分が使えなくなるリスクもあるのです。
また、商標と混同されやすい権利に意匠権や特許権もあります。それぞれ守る対象が異なるため、以下のように整理して覚えておくとわかりやすいでしょう。
商標権 商品名・サービス名、ロゴなど「ブランドの名前」を守る
意匠権 商品の「デザイン」や「形」を守る
特許権 新しい「技術」や「アイデア」を守る
守りたい対象によって申請すべき権利は異なります。
自分のビジネスや商品に合った保護の仕組みを選ぶことが大切です。
商標登録で守れる「名前・ロゴ・アイデア」の範囲
商標登録で守れるのは名前やロゴだけではありません。
条件を満たせば、音や色の組み合わせ、立体的な形、ホログラムなども商標として登録できます。
実際のビジネスでは、表記がほんの少し違うだけでもトラブルに発展することがあるため注意が必要です。
たとえば以下のようなケースです。
カタカナ表記の微妙な差(「サクラ」と「サクーラ」)
英語スペルの違い(「Color」と「Colour」)
また、近年では SNSアカウント名やYouTubeの動画シリーズ名など、デジタル上の名称も商標として出願されるケースが増えています。
ネットでの発信やコンテンツを収益化している方は、今後のリスクに備える意味でも登録を検討してみましょう。
さらに、登録後に自分の商標が無断で使われてしまった場合は、使用の差し止めや損害賠償の請求が可能です。
文房具メーカーが模倣品に対して販売中止を求めた実例もあり、正当な権利として主張できる強みがあります。
商標登録しないリスクとは?事例で学ぶ3つの落とし穴
商標を登録しないままビジネスを始めると、思いがけないトラブルに発展する恐れがあります。
たとえば、長年使っていたブランド名を他人が先に登録すると、自分がその名前を使えなくなってしまうのです。
ブランド名を失えば、それまで積み重ねてきた信用やイメージが一気に崩れてしまうでしょう。
ビジネスの継続にも影響が及び、新たな名前に変更してゼロからブランドを築き直さなければならないかもしれません。
商標は、ただの申請手続きではありません。
大切な名前やロゴを守り、ビジネスの価値を高めてくれる「無形の資産」といえる存在です。
ビジネスの土台を安心して築くためにも、「商標登録」は最初に検討すべき一手といえるでしょう。
出願前に確認したい3つの準備ポイント

登録できる商標とできない商標の違い
商標として登録するには、いくつかの基準を満たす必要があります。
なかでも注意したいのが、識別力の弱い商標や、公序良俗に反する表現など、登録が認められにくいケースです。
以下のような例に該当する場合は、商標としての登録が難しくなる可能性があります。
識別力が弱い名称
「東京せんべい」など、地名と商品名を組み合わせただけのものは、他の商品と区別する力が乏しいと判断されやすくなります。
商品の特徴や品質をそのまま表した言葉
「やわらかクッション」など、商品の性質を説明するだけの表現は、一般的すぎて独占できないと見なされます。
ごく一般的でありふれた表現
「おいしいパン」など、誰でも使うような表現は独自性に欠け、商標として保護されにくくなります。
公序良俗に反する単語や表現
不適切なスラングや差別的・侮辱的な言葉などは、社会的に不適切とされ、過去にも拒絶された例があります。
有名ブランドに酷似した名称
海外の著名ブランド名の一部だけを変更した名称などは、模倣とみなされ、登録が認められないことがあります。
商標検索(J-PlatPat)で事前に調査する方法
出願の前には、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を使って、似たようなものが既に登録されていないかを確認しておきましょう。
【検索の基本手順】
- J-PlatPatにアクセスする
- 「商標」タブを選ぶ
- 商標名を入力し、「部分一致」や「前方一致」などで検索する
- 結果一覧から類似する商標がないかをチェックする
表記の揺れ(ひらがな/カタカナ/英語など)も含めて調べることがポイントです。ロゴマークの出願を考えている場合は、図形コード検索もしてみましょう。
【調査の進め方(例)】
- まずは「完全一致」で登録済みかどうかを確認する
- 続いて「類似検索」で近い名称が使われていないか調べる
- 該当のビジネス内容に応じて、区分ごとに対象を絞り込む
このように丁寧に事前調査を行うことで、スムーズに登録へと進める可能性が高まります。
また、海外でも同じブランド名を展開したい場合は、マドプロ出願(国際商標登録制度)を活用するとよいでしょう。複数の国に効率よく商標保護を広げられます。
区分(45区分)の選び方と注意点
商標は、登録したい商品やサービスの内容に応じて「区分」というカテゴリに分類されています。
出願時には、自社に該当する区分を正確に選ぶ必要があります。
ただし、この判断を誤ると後々トラブルにつながる恐れがあります。
たとえば以下のような事例です。
アパレルブランドが衣類だけに商標をかけ、アクセサリーや雑貨類を登録しなかった結果、模倣品に対応できなくなってしまった。
実際には使用予定のない区分まで出願したことで、費用が無駄に膨らみ、使われない権利だけが残った。
一方で、ECサイトや複数の事業を展開しているケースでは、はじめから複数区分を申請しておくことで安心感につながったという例もあります。
将来的な展開を見越した計画的な対策として、有効だったといえるでしょう。
なお、区分の分類は定期的に見直されています。特許庁の公式サイトやJ-PlatPatの分類検索ツールを活用し、最新の情報を把握しておくと安心です。
商標登録を自分で行うための5ステップ

ステップ① 登録したい名称やロゴを決める
ブランド名やロゴは、他と区別しやすく、覚えやすいものを考えることが大切です。ビジネスの印象を左右する重要な要素なので、独自性を意識して設計しましょう。
よくあるつまずきと対策
単語が一般的すぎて識別力が弱い場合 → 造語や独自性のある言葉を意識しましょう。
他社の商標と混同しやすい場合 → J-PlatPatであらかじめ類似調査を行っておきます。
ステップ② 商品やサービス内容に合った区分を選ぶ
商標は45の区分に分かれており、自分の事業内容に合わせて適切な区分を選ぶ必要があります。必要に応じて複数区分を同時に出願することも検討しましょう。
よくあるつまずきと対策
関連する商品・サービスを見落としてしまう場合 実際に扱う内容をリストアップして整理しておきます。
誤った区分を選んでしまう場合 特許庁の「商品・役務サポートツール」で事前に確認しておきましょう。
ステップ③ 類似する商標を事前に調べておく
出願しても必ず登録されるとは限らないため、J-PlatPatを使って同一または類似の商標が登録されていないかを事前に確認しておくことが重要です。
表記のゆれ(ひらがな・カタカナ・英語など)にも注意しながら、複数の検索パターンを試してみましょう。
ステップ④ 願書を作成し、特許庁に出願する
願書は、特許庁のフォーマットに沿って作成し、電子出願または書面で提出します。
作成時には、次のような点に注意しましょう。
- フォントや文字サイズは、所定のルールに従います。
- 色付きロゴを登録する場合は、色の指定や図案の添付が必要です。
- 商標見本の画像データは、JPEG形式などの対応形式を確認しておきましょう。
電子出願を行う際は、電子出願ソフトを使って入力・送信を行います。
操作画面は比較的わかりやすく、テンプレートも用意されているため、初めての方でも安心です。
ステップ⑤ 出願後の流れとスケジュールを把握する
出願後は、特許庁による形式審査と実体審査が行われます。問題がなければ「登録査定」の通知が届きます。
その後、指定された登録料を納付することで、商標権が正式に発生します。
「早期審査制度」を利用すれば、審査期間を短縮できる場合もあります。
通常の審査には5〜8カ月ほどかかるため、急ぎの場合は、この制度の活用も検討してみてください。
登録までの流れをあらかじめ把握しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
費用・期間・手間で比較する3つの出願スタイル
商標出願には、主に3つの方法があります。それぞれにかかる費用やサポート内容、注意点などが異なるため、自分に合ったスタイルを選ぶことが大切です。
| 出願スタイル | 費用の目安 | 主なメリット | 注意したいポイント | 実際の声・事例 |
| 自分で手続きする | 約4万円前後 | 費用を抑えられる | 記載ミスによって出願が拒否されることがある | 記載ミスで拒絶通知を受けた体験談あり |
| 弁理士に依頼する | 7〜10万円程度 | 専門家のサポートが受けられて安心 | 費用が高くなりやすい | 拒絶通知後に補正して登録できた成功例あり |
| オンライン代行を使う | 3〜5万円前後 | サポートがありつつ、費用も比較的お手頃 | サポート範囲に限りがある | 手続きがシンプルで満足という比較口コミあり |
登録後に備えておきたい2つの重要ポイント

商標の更新と管理体制の重要性
商標登録が完了したあとも、安心はできません。商標権を有効に保つには、定期的な更新手続きと日々の管理が欠かせないためです。もし更新のタイミングを逃すと、せっかく取得した権利が失効してしまう恐れがあります。
実際に、中小規模の事業者で「更新通知に気づかず、商標が無効になってしまった」というトラブルが発生しています。
このような事態を防ぐためには、更新日をカレンダーに登録したり、アラートを設定したりするなど、あらかじめ対策をとっておくと安心です。管理台帳を整備しておくことも、忘れ防止につながります。
最近では、更新時期を自動で知らせてくれる便利な管理サービスも登場しています。少人数で運営しているEC事業者や中小企業にとって、こうしたサービスの活用は心強いサポートとなるでしょう。
権利トラブルへの備えと対応の流れ
商標権を侵害されてしまった場合は、できるだけ早く対応することが重要です。状況に応じて適切な手順を踏むことで、スムーズに解決へとつながる可能性が高まります。
まずは、相手に警告書を送りましょう。
その際には、自社が商標権を保有していることを明確に伝え、誤解や無断使用をやめるよう求めることが大切です。
その後は相手の反応を見ながら交渉を進め、必要に応じて法的措置も視野に入れます。
たとえば、ある文具メーカーでは、自社ロゴに似たデザインが他社商品に使われていたことから、警告書を送付しました。交渉を重ねた結果、相手企業が商品デザインを変更し、謝罪を表明したという事例があります。
このようなトラブルを未然に防ぐには、商標の使用状況や類似商標の有無を定期的にモニタリングしておくことが効果的です。
不安なときは、弁理士など専門家の力を借りることで、確実で安心な対応につながります。
拒絶理由通知への対応と成功事例
万が一、出願後に拒絶理由通知が届いたとしても、あきらめる必要はありません。
通知の内容を丁寧に確認し、必要に応じて説明文を加えたり、商標の表現を見直したりすることで、登録につながる可能性があります。
たとえば、あるスタートアップ企業では「識別力が弱い」と判断されて一度は拒絶理由通知を受けました。しかし弁理士と相談しながら補足資料を提出した結果、最終的に商標登録が認められた、という事例もあります。
拒絶通知への対応は専門的な判断が求められることも多いため、自力で出願した場合でも、弁理士に相談するのがおすすめです。
【余談】話題のニュースに学ぶ「商標」のリアル
2023年7月には、Apple社が「リンゴ」の図柄を商標登録しようとした件がニュースで話題になりました。
スイスの農家団体と、果物に関する商標権をめぐって争いが生じたのです。
一見すると、大企業だけの話に見えるかもしれません。
しかし、こうしたトラブルは中小企業や個人事業者にとっても他人事ではありません。
大切なロゴやブランド名を守るには、できるだけ早く商標登録を済ませることが重要です。
さらに、定期的な管理や見直しも欠かせません。
ブランドの価値を守るためには、万が一のリスクに備える姿勢が求められます。
この備えがあるかどうかが、長く信頼されるブランドになれるかどうかを左右します。
まとめ|商標登録の第一歩は「知ること」から

商標登録は、あなたの大切なブランドやビジネスの信用を守るための強力な手段です。
「まだ小さな事業だから」「費用がかかりそうで不安」といった理由で後回しにすると、思わぬトラブルを招く可能性があります。
本記事では、商標登録の基本から手続きの流れ、費用・期間・区分の選び方、さらに登録後の注意点までを解説しました。
また、実際に起きたトラブル事例やニュースを通じて、商標権が現実のビジネスにどれほど密接に関わっているかもお伝えしました。
まずは、自分のビジネスに必要な名前・ロゴ・サービス名などを洗い出し、J-PlatPatで商標検索を行ってみましょう。
早めに行動を起こすことが、あなたのブランドを守る最善の方法です。
しっかりと商標を守っておくことで、安心してビジネスを育てていける未来につながります。